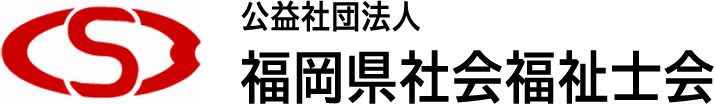

高齢者やその家族に対して、暮らしの困難の軽減や解決に向けた支援組織・制度・サービスなどを活用し、高齢者の暮らしを支えています。
地域包括支援センターや高齢者相談窓口で、地域で暮らす高齢者や、地域の中で孤立した高齢者、高齢者を介護する家族の悩みやニーズを聞き支援につなげ、介護の現場では、生活の相談や家庭での暮らしへの復帰相談などを受け、さまざまな専門職や家族と協力・連携して支援を行います。要介護認定を決めるための調査をする介護認定審査会の調査員を担ったり、高齢者虐待への対応、認知症など判断能力が不十分になった方の権利を守り生活を支援する「成年後見制度」や、関係機関との調整・連携など、幅広く活動しています。
 相談窓口
相談窓口地域包括支援センター
お住いの市町村や区にある高齢者相談窓口

障がいのある人が自ら望む生活を営むことができるように、障がい福祉サービス事業所や行政機関、医療機関、教育、労働、司法など、社会のさまざまな領域で支援を行なっています。社会のなかで自立した生活を営むための就労支援や、地域社会の中で快適に暮らすための生活の支援、成年後見制度を活用した権利擁護など、それぞれの状況に応じた支援と関係機関との調整を行います。
すべての人が平等に持っている権利が制限される状況を解消するために、社会の仕組みや人々の意識に働きかけるなど、ともに生きる社会づくりに取り組んでいます。
 相談窓口
相談窓口市町村基幹相談支援センター
お住いの市町村や区にある障がい者相談窓口

病気や怪我をすると、生活や仕事・学校への影響、経済的な心配など、さまざまな不安を抱えることになります。患者やその家族が抱える課題に共に向き合い、利用できるサービスや制度などの情報を提供し、必要に応じて利用できるように調整を行います。退院後も安心して生活できるように、関係機関との連携やネットワークづくりに貢献しています。
 相談窓口
相談窓口各医療機関
行政の相談窓口
保健所
市町村保健センター
精神保健福祉センター

本当に困っている人ほど助けを求めることが難しい場合があります。就労の課題、心身の不調、家計の問題、家族問題など、多様で複合的な課題・問題を持つ人が「制度の狭間」に陥らないよう、社会福祉士は幅広く対応します。一人ひとりの困難な状況を適切に把握し、切れ目のない継続的な支援となるよう、連携していきます。
また生活課題を抱えた人を早期に把握できるよう、地域の住民や自治体などとも連携して共生できる地域づくりに取り組んでいます。
 相談窓口
相談窓口社会福祉協議会
社会福祉士会
お住いの市町村や区にある各相談窓口(行政窓口)

こどもの権利が守られていくためには、その背景にある家庭環境が大切です。
虐待や貧困、障がいや、心の悩み、子育てが困難な状態など、さまざまな問題に対応できるようこどもや家庭を支える多くの支援機関や支援員がいます。
社会福祉士は、こどもが安心して過ごせる居場所づくり、こどもが自分の意見を言うためのサポート、子育て支援サービスの提供など、幅広い関係者や地域の支援機関と協力し合って、こどもと家族の暮らしを支えます。
 相談窓口
相談窓口児童相談所
児童相談所虐待対応ダイヤル189
市区町村こども家庭センター(子育て世代包括支援センター・子ども家庭総合支援拠点)
子ども家庭支援センター
家庭児童相談室
お住いの市町村や区にある相談窓口

不登校やいじめに関する相談、特別支援教育、児童虐待など、学校に関するこどもの悩みを受け止め、一人ひとりに応じた居場所や学び方を一緒に見つける支援を行っています。
学校内にはスクールソーシャルワーカーが配置され、学校外では相談窓口などに専門のソーシャルワーカーがいます。
 相談窓口
相談窓口各地区教育委員会
児童相談所
各市町村特別教育相談センター

お住いの市区町村にある各相談窓口で、高齢者や障がい者への対応、こどもや家庭に関する対応、差別被害者への対応や、ホームレスの自立支援、日本に暮らす外国人の支援など、幅広い分野の相談に対応しています。地域住民のさまざまな悩みや問題を把握し、解決につながる制度やサービスに結びつけるため、多くの関係機関や専門家と連携し、施策の作成や調査、支援のネットワークづくりを行っています。
 相談窓口
相談窓口お住いの市町村や区にある各相談窓口(行政窓口)

平穏な日常が脅かされた犯罪被害者へは、身体的、精神的、経済的な影響へのケアや、捜査や裁判に伴う問題や負担への対応といった支援が必要です。被害者に寄り添いながら話を聞き、被害の状況を整理したり、他機関へ向けて思いを代弁するなど、日常を取り戻すためのサポートを行います。警察や医療、司法などさまざまな機関と連携して、必要な支援のコーディネートを行います。
一方、犯罪加害者が社会復帰するための支援も行っています。罪を犯した人の背景には、障がいや生活困窮の問題がある、社会から孤立して必要な支援が受けられていないなどの場合もあります。犯罪を繰り返さないよう、本人の問題を理解し、地域でのつながりをつくるなど、地域社会への働きかけも行っています。
 相談窓口
相談窓口弁護士
各区の行政の法律相談会
各地の障がい者基幹相談支援センター
地域包括支援センター
法テラス

働くことや就職することが困難な幅広い方々への就労支援を行っています。また日本で暮らす外国人への、生活や就労で生じるさまざまな問題やニーズに対する相談援助も行っています。多様な文化への理解を促進し、職業訓練や就職活動のサポート、働きやすい環境づくり、居場所づくりなどの場でも活躍しています。
 相談窓口
相談窓口ハローワーク
社会福祉協議会
お住いの市町村や区にある相談窓口

地震や水害など大きな災害時には、障がい者や高齢者、地域住民の中でひとりで避難することが困難な方へのサポートが重要です。混乱した被災時にスムーズに支援に入れるよう、福岡県社会福祉士会は福岡県と災害協定を結んでいます。災害発生時には、災害支援ボランティアとしての活動支援や、さまざまな職種の福祉人材で構成された福岡県災害派遣福祉チーム(DWAT)として派遣要請地域で活動を行います。また他県の社会福祉士のチームと連携し、避難所受付や避難所の巡回、相談窓口の運営や避難者の健康管理など、避難所支援を行います。
被災者の心理を理解し災害時の支援制度等を学び、被災地の復興支援の一助となるよう活動します。
 相談窓口
相談窓口社会福祉協議会
福岡県社会福祉士会災害支援委員会










 TOP
TOP